

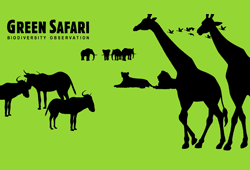 「GREEN SAFARI」サイト
「GREEN SAFARI」サイト |
|
 「GREEN SAFARI」アニマルインフォメーション
「GREEN SAFARI」アニマルインフォメーション |
「GREEN SAFARI」スタートのお知らせ
2010年は国連が定める「国際生物多様性年」。WWFジャパンでは5月、この生物多様性をテーマとした、参加型のオンライン自然保護プログラム「GREEN SAFARI(グリーンサファリ)」をスタートしました。
バーチャルな野生の世界を楽しみながら、リアルに生物多様性の保全に貢献できる。それが「GREEN SAFARI」の最大の特徴です。
ブログで広がれ!生物多様性の保全
「GREEN SAFARI)」のメインツールは、緑のブログパーツ。
自分のブログに貼りつけると、そこに現れるCGの野生生物の生態をサファリ感覚で観察することができます。しかも、長期間ブログに貼り続けるほど、動物の種類や出現の頻度が増え、こちらに近寄ってくるシーンを見ることができる設定になっています。
このブログパーツは、WWFジャパンの会員になると、ダウンロードできる仕組みになっており、実際、ユーザーの方々にお支払い頂いた会費は、WWFジャパンが実際に行なっている生物多様性保全のための活動資金として活かされることになります。
つまり、「GREEN SAFARI」に参加するユーザーが増えるほど、バーチャルな世界に緑が広がると同時に、WWFのリアルな活動に使われる資金が生まれ、地球の生態系保全を推進する力が強まっていく仕組みになっています。
「GREEN SAFARI」に参加してみませんか?
「生物多様性」とは、さまざまな生き物たちが互いに複雑なつながりを保ちつつ、地球というひとつの星に共存している状態のこと。そして、私たちの暮らしを根底から支えてくれているものでもあります。
「生物多様性」は、地球環境の保全を考える上で、最大のキーワードと言っても過言ではありません。
しかし今、この「生物多様性」が、急激に世界の各地で失われつつあります。
過去400年間に、わかっているだけで700種以上の野生生物が絶滅しました。ゾウやライオンといった、おなじみの野生動物たちも、多くが、絶滅の危機にさらされています。
そして、その背景には、私たちの目にはふれないような、小さな生きものたちの減少と、自然環境の悪化が進む、深刻な現状があるのです。
「GREEN SAFARI」は、地球環境を守るために何かしたいと願っている人たちに、新しい参加の機会を提供するプログラムです。
WWFは、「GREEN SAFARI」をとおして、この地球をわかちあっている野生生物への関心がさらに高まり、生物多様性保全への理解が広まっていくことを期待しています。
GREEN SAFARIウェブサイト
関連ニュース
【セミナー開催報告】ペット取引される爬虫類
-上野動物園×WWF・トラフィクセミナー-
2017年09月25日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催しました。生息地の開発や、ペットにするための捕獲、密輸により、絶滅の危機に瀕しているカメやトカゲなどの爬虫類。これらの動物は、密輸される途中で保護されても、多くは生息地に帰ることができません。なぜでしょうか?こうした日本のペットショップで販売される爬虫類の取引の現状と問題について、専門家が解説。参加者の疑問に答えました。
©トラフィック
【セミナー開催のご案内】上野動物園×WWF・トラフィックセミナー
-ペット取引される爬虫類-
2017年08月23日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催します。動物園で飼育されている爬虫類の生態やペット人気の陰で絶滅の危機に瀕している種を守るための取り組みと、日本のペットショップで販売されている爬虫類の取引を巡る課題などを専門家が分かりやくお話しします。
© Michel Terrettaz / WWF
2017年08月08日
2017年8月8日、トラフィックは、日本の主要eコマースサイトでの象牙取引を調査した報告書を発表した。調査の結果、オンライン店舗のほか、ネットオークションや個人向けフリマサイトでも活発な取引が行なわれる中、現状の規制に大きな課題があることが明らかになった。今回の調査で、これまで不明瞭だった、特にインターネットを通じた象牙取引の一端が明らかになったことから、日本政府にはあらためて、違法取引を許さない包括的な規制措置を求めていく。
©Martin Harvey / WWF
2017年07月18日
2017年7月4日、香港税関は葵涌(クワイチョン)でコンテナに隠された7.2tの密輸象牙を押収した。年に2万頭を超えるアフリカゾウが密猟されている中で起きた今回の摘発は、過去30年で最大級の規模と見られており、象牙の違法取引をめぐる国際的な組織犯罪の深刻さを物語っている。こうした一連の野生生物の違法取引に問題に対し、各国政府は今、強く連携した取り組みを進めようとしている。合法的な象牙の国内市場を持つ日本にも、この流れに参加する積極的な姿勢と取り組みが強く求められている。
©Keiko Tsunoda
関連出版物
Wildlife Cybercrime in China:E-commerce and social media monitoring in 2016
発行:TRAFFIC【2017年5月】 著者:Yu Xiao, Jing Guan, Ling Xu【英語】Briefing Paper
RhODIS® (Rhino DNA Index System): Collaborative Action Planning Workshop Proceedings
発行:TRAFFIC【2017年2月13日】 著者:Ross McEwing, Nick Ahlers【英語】30pp







