

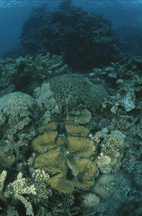 オオシャコガイ オオシャコガイ©WWF-Canon / Jurgen FREUND |
ワシントン条約は、生きているものだけではなく附属書に掲載されている種の部分や派生物の国際取引も規制している。附属書Ⅱ掲載種であるオオシャコガイTridacna gigas は真珠の養殖に必要な核としても利用されているが、日本に輸入される際にきちんと輸出国から輸出許可書を得ているだろうか。条約対象種の取引状況が確認できる年次報告書の記録からは、核としての輸入が読み取れず、輸入状況を確認することは難しい。
現在流通している海水産の養殖真珠は、通常アコヤガイを真珠母貝として養殖されたもので、そのほとんどは、真珠層を持つ他種の貝から造った球状の核と、ピースと呼ばれる母貝の外套膜の細胞小片を母貝に挿入して養殖する。この核は真珠核と呼ばれ、米国のミシシッピー川などに生息するイシガイ科のドブガイ Anodonta woodiana の貝殻を球状に加工したものを使用することが多い。ドブガイの貝殻は真珠層の構造を持ち、養殖真珠の核とするには最適であるといわれている。しかし、このドブガイからできる真珠の核よりも、より安価な真珠層を持たないオオシャコガイやプラスチックを核として利用する場合がある。オオシャコガイの貝殻は大きく、その厚い層からドブガイと比べて大きな核を数多く造ることができる。日本へは養殖真珠用として核そのものが輸入される場合と、オオシャコガイの核を有する養殖真珠が輸入される場合がある。
養殖真珠のできるまで
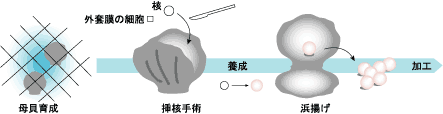
ワシントン条約識別マニュアルによると、シャコガイTridacnidae には7種あり、一番大きなものがオオシャコガイで、殻長が1.4mに達することもある。沖縄から北オーストラリアにかけての西太平洋に分布し、ハワイなどの様々なところへ移殖されている。IUCNのレッドデータリストによると、その生息状況は危急種(VU)と記載されている。オオシャコガイは、その貝殻が観賞用に、その身が食用に利用されてきており、インド太平洋海域のいたるところでは劇的にその生息数が減少している。その要因のひとつとして、貝殻部分と軟体部分を利用するための過剰な捕獲があげられる。沖縄でも現在海中で生きている姿を見ることはほとんどないが、かつてはその大きさを利用して芋を洗うなどのたらいの役目を果たしていたことが知られている。
 ©TRAFFIC East Asia-Japan |
ワシントン条約では、まずオオシャコガイが1983年から附属書Ⅱに、続いてシャコガイ科全種が1985年から附属書Ⅱに掲載されている。日本の輸入量は、生きているものが1999年に160個体、2000年に390個体、2001年に57個体が輸入され、形態が不明のものが2000年に150輸入されている。2000年に輸入されたもののうち、392個(生きているもの390、貝殻2)は科学研究目的で輸入されており、それ以外は商業目的である。これらの原産国としてパプアニューギニア、ソロモン諸島、フィリピン、インドネシアが報告されている。この報告からは養殖真珠用の核の輸入が含まれているかどうかは不明である。しかし、業界へのインタビューによると、核としてのオオシャコガイ、オオシャコガイの核を含む養殖真珠、もしくはオオシャコガイの核を有する模造真珠の輸入にワシントン条約の輸出許可書が必要という認識は業界内にあまり広まっておらず、ほとんと許可書なしで輸入しているのではないかとの話である。
条約ではオオシャコガイの大きさや形状に関わらずその部分と派生物も規制している。真珠の養殖用の核であっても、条約で必要とされている手続きをとらなければならない。輸入する際には、輸出国政府が発行した条約の輸出許可書とともに輸入し、その取引量を記録することができなければ持続可能な利用を考えることはできない。
関連ニュース
【セミナー開催報告】ペット取引される爬虫類
-上野動物園×WWF・トラフィクセミナー-
2017年09月25日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催しました。生息地の開発や、ペットにするための捕獲、密輸により、絶滅の危機に瀕しているカメやトカゲなどの爬虫類。これらの動物は、密輸される途中で保護されても、多くは生息地に帰ることができません。なぜでしょうか?こうした日本のペットショップで販売される爬虫類の取引の現状と問題について、専門家が解説。参加者の疑問に答えました。
©トラフィック
2017年07月18日
2017年7月4日、香港税関は葵涌(クワイチョン)でコンテナに隠された7.2tの密輸象牙を押収した。年に2万頭を超えるアフリカゾウが密猟されている中で起きた今回の摘発は、過去30年で最大級の規模と見られており、象牙の違法取引をめぐる国際的な組織犯罪の深刻さを物語っている。こうした一連の野生生物の違法取引に問題に対し、各国政府は今、強く連携した取り組みを進めようとしている。合法的な象牙の国内市場を持つ日本にも、この流れに参加する積極的な姿勢と取り組みが強く求められている。
©Keiko Tsunoda
2017年07月10日
楽天株式会社が楽天市場での象牙製品の販売行為を今後認めないことが明らかになった。現在、日本国内で合法的に販売されている象牙製品は、近年のアフリカゾウの密猟とは因果関係がないとされている。しかし、トラフィックの新たな調査でも、急成長を続けるeコマースを通じた象牙取引については、法律の整備が追いつかず、対応しきれない状況が続いていることが明らかになっており、トラフィックとWWFジャパンも厳しい措置を求めていた。日本のe-コマース企業の判断としては、大規模な今回の楽天の決定が、他企業にもより厳しい対応を迫るものとなることが期待される。
©Steve Morello / WWF
2017年06月22日
2017年6月20日に象牙18本を違法取引した容疑で、都内の古物商と従業員、その顧客ら27人が書類送検されるという大規模な事件が報道された。世界では、ゾウの密猟と象牙の違法取引に歯止めをかけるため関係国が抜本的な対策に着手する中、日本国内の違法取引が意味するところとは何か。国内市場管理の問題点と、トラフィックとWWFジャパンが提言する国内違法象牙ゼロに向けた課題を紐解く。
@Martin Harvey / WWF
関連出版物
The Southern Bluefin Tuna Market in China
発行:TRAFFIC Hong Kong【2017年6月】 著者:Joyce Wu【英語】50pp
The Shark and Ray Trade in Singapore
発行:TRAFFIC,Malaysia【2017年5月】 著者:Boon Pei Ya【英語】59pp







