

メバチの危機的状況に目を向けるべき
 市場にならぶメバチマグロ、ハワイ ©WWF / Lorraine Hitch 市場にならぶメバチマグロ、ハワイ ©WWF / Lorraine Hitch |
【英国、ケンブリッジ発 2007年11月21日】
不適切な漁獲を取り締まるべき当局が、メバチにも過剰な捕獲がおよんでいる現状を認識できていないがために、このマグロは危機的状況に置かれている。
野生生物取引をモニタリングする団体であるトラフィックがこのほど新たにまとめた報告書によると、太平洋東部では、メバチの漁獲量の最大60%がまだ繁殖能力のない幼魚であり、その漁獲の割合は増加傾向にある。
「成魚に達する前に幼魚を捕獲してしまうことは、マグロ資源の持続可能性を脅かすことになり、日本における価値の高い刺身のためのマグロを入手するのが困難になってしまうことを意味する」とトラフィックの海洋プログラムリーダーであるグレン・サントは言う。「刺身として食卓に上る前に、缶詰という形でメバチは一生を終えることになる。こうして、マグロ資源は、枯渇の瀬戸際に立たされている。メバチ漁業の生物学的、経済学的な未来は深刻な危機に直面している。」
今回の報告書によれば、太平洋東部、太平洋中・西部、大西洋、インド洋におけるメバチはすべて過剰に漁獲されるか、それに近い状態である。(表を参照) 大西洋では資源の減少が続いており、この漁獲量でも過剰である。
メバチは日本の刺身市場で価値が高いが、適切に管理された漁業をおこなわなければ、大西洋のクロマグロやミナミマグロのように絶滅の危機に瀕してしまうだろう。すでにIUCNのレッドリストで絶滅危惧種に分類されているのが現状だが、さらにひどくなるおそれがある。かつて刺身は日本が唯一の大きな消費国であったが、今では米国、EU各国、韓国、台湾、中国でも顕著に消費が増えているのであるから。
危機を回避する方法としては、予防原則に立った漁獲枠の設定、メバチの資源回復計画の導入、幼魚の捕獲禁止、漁獲量についてのより正確なデータ収集(インドネシアやフィリピンなどにはFAOデータがない)などがあげられる。データ不備の例をあげると、日本、EU、米国の輸入統計からインドネシアは2004 年に8821 t 輸出していることがわかるが、FAOのデータ上はゼロである。
科学的調査が示すところでは、メバチの漁獲量を大きく減らす必要があるが、この科学的助言は顧みられることがなかった。公海でのメバチは獲り尽くされようとしている。世界各国が協調して効果的な措置を講じなければ、重要な水産資源が永遠に失われてしまうことになるだろう。
報告書によれば、公海での漁業を規制すべき責務を負う国際的な枠組みであるRFMO(地域漁業管理機関)に所属する各国政府は、多くの場合、科学的助言への対応が遅く、メバチの過剰漁獲の問題にきちんと取り組めていない。また、UNFSA(国連公海漁業協定)のもとでの、法的な義務を満たすことができないでもいる。
メバチの資源が枯渇すれば、水産業に大きな負の経済的影響を与えるだろうし、関連した加工産業や流通業界にも影響をおよぼすだろう。そして、メバチの漁業船団からの収入に頼っている数々の島嶼国も打撃を免れない。
今回の報告書は、太平洋中西部におけるメバチの管理を担当するWCPFC(西部太平洋マグロ類委員会)が、12月3日~7日にグアムで開催されるのにあわせてまとめられたものである。トラフィックでは、WCPFCのメンバー各国が、その国際的責務を果たすように行動することを求めるものである。そして、手遅れになる前に、「メバチの漁獲量をWCPFC各メンバー国は減らすべきである」という科学委員会の勧告を履行することを求める。
報告書(英文:PDFファイル)は、こちら 『With an eye to the future: addressing failures in the global management of Bigeye Tuna』
補足資料
-2007年11月21日報道発表 「メバチマグロの危機的状況に目を向けるべき」-
| 持続可能な漁獲量の最大値 (Maximum Sustainable Yield) | 2005年の漁獲量 | |
| 大西洋 | 93,000-114,000 t * | 60,453 t |
| インド洋 | 111,200 t | 112,400 t |
| 太平洋東部 | 106,722 t | 102,376 t |
| 太平洋中・西部 | 110,000-120,000 t | 157,102 t |
出典:Hampton, Langley and Kleiber2006 Stock Assessment of Bigeye Tuna in the Western and Central Pacific Ocian; ICCAT2005 Report for Biennial Period; IATTC2006 Report of the 74th Meeting of the inter-American Tropical Tuna Commission; IOTC2006 Report of the Ninth Session of the Scientific Committee;WCPFC2006 Scientific Committee Second Regular Session
FAO統計による輸入数量 (単位: t ) の国別グラフ
| 鮮魚でのメバチマグロの輸入国(2004) | 冷凍魚でのメバチマグロの輸入国(2004) |
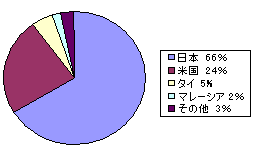 | 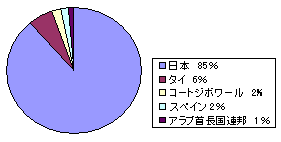 |
出典:FAO2007 Species Fact Sheet Thunnus obesus | |
<ひとくちメモ>
1.1995-2005年の漁獲量の上位国は日本(23.5%)、台湾(19.5%)、インドネシア(7.6%)、スペイン(7.1%)。2005年だけの漁獲量をみても、この順位は同じで、それぞれ19.1%, 18.3%, 8.9%, 6.4%。
2.IUU漁業(違法で、規制のない、報告されない漁業)が脅威となっている。輸出入の統計をもっと厳密にとることで、IUU漁業を減らしていけるはず。
3.持続的な漁業のためには、MSCのような漁業認証制度を漁業者、加工業者、小売業者等のあらゆる段階で導入することが必要。そうすれば消費者が由来のたしかな魚を選択できるようになる。
■上記データの詳細についてはレポートをご参照ください。
★ 報告書(英文:PDFファイル)は、こちら 『With an eye to the future: addressing failures in the global management of Bigeye Tuna』
■ 詳細に関するお問合せ先
トラフィック イーストアジア ジャパン 石原明子 tel03-3769-1716/広報 大倉寿之(WWFジャパン)
Glenn Sant, TRAFFIC international (Global Marine Programme) email: GSant@trafficint.org
関連ニュース
【セミナー開催報告】ペット取引される爬虫類
-上野動物園×WWF・トラフィクセミナー-
2017年09月25日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催しました。生息地の開発や、ペットにするための捕獲、密輸により、絶滅の危機に瀕しているカメやトカゲなどの爬虫類。これらの動物は、密輸される途中で保護されても、多くは生息地に帰ることができません。なぜでしょうか?こうした日本のペットショップで販売される爬虫類の取引の現状と問題について、専門家が解説。参加者の疑問に答えました。
©トラフィック
国内での象牙取引で違法事例再び
古物商ら12人が書類送検されるも不起訴に
2017年08月30日
2017年8月25日に象牙9本を違法に取引した容疑で、東京都内の古物商と従業員、その顧客ら12人が書類送検されるという事件が報道された。これは、6月20日に同じく18本の象牙を違法に取引した業者が書類送検された事件に続き、2017年で2件目の摘発となる。さらに29日には、不起訴処分となったことが明らかになった。世界では、ゾウの密猟と象牙の違法取引に歯止めをかけるため関係国が抜本的な対策に着手する中、日本国内で相次ぐ違法な象牙の取引。国内市場管理の問題点があらためて浮き彫りになっている。
©Martin Harvey / WWF
【セミナー開催のご案内】上野動物園×WWF・トラフィックセミナー
-ペット取引される爬虫類-
2017年08月23日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催します。動物園で飼育されている爬虫類の生態やペット人気の陰で絶滅の危機に瀕している種を守るための取り組みと、日本のペットショップで販売されている爬虫類の取引を巡る課題などを専門家が分かりやくお話しします。
© Michel Terrettaz / WWF
2017年08月08日
2017年8月8日、トラフィックは、日本の主要eコマースサイトでの象牙取引を調査した報告書を発表した。調査の結果、オンライン店舗のほか、ネットオークションや個人向けフリマサイトでも活発な取引が行なわれる中、現状の規制に大きな課題があることが明らかになった。今回の調査で、これまで不明瞭だった、特にインターネットを通じた象牙取引の一端が明らかになったことから、日本政府にはあらためて、違法取引を許さない包括的な規制措置を求めていく。
©Martin Harvey / WWF
関連出版物
The Southern Bluefin Tuna Market in China
発行:TRAFFIC Hong Kong【2017年6月】 著者:Joyce Wu【英語】50pp
The Shark and Ray Trade in Singapore
発行:TRAFFIC,Malaysia【2017年5月】 著者:Boon Pei Ya【英語】59pp







