

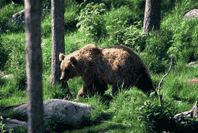 ヒグマ ヒグマ©WWF-Canon/Michel GUNTHER |
【2006年4月5日 英国、ケンブリッジ発】
トラフィックヨーロッパの新しいレポート” Bear Necessities: An analysis of Brown Bear management and trade in selected range States and the European Union's role in the trophy trade”によれば、ヒグマはヨーロッパの狩猟者にとってもっとも人気があり価値のあるハンティングトロフィーであり、欧州連合(EU)はヒグマのトロ フィーの主要な輸入国のひとつである。ヒグマの個体数は生息国である49ヵ国のほぼ半数で減少していると考えられており、人為的な死亡、なかでもハンティ ングはこれらの減少の主な原因のひとつである。このレポートでは、欧州委員会(European Commission)の依頼により、ヒグマの生息している9ヵ国の管理、トロフィーハンティング、トロフィーの取引、規制に関する情報をまとめている。
「わたしたちは、このレポートがヒグマについて研究する人々に有用な情報を提供し、まだ管理計画を持っていない生息国に策定を促すことになるだろう」と著者であるトラフィックヨーロッパのアメリー・ナップは言う。
このレポートでは、ヒグマのトロフィーの国際取引について分析し、生息国であるブルガリア、クロアチア、エストニア、ルーマニア、ロ シア連邦、スロバキア、スロベニア、カナダ(ブリティッシュコロンビア)と米国の9ヵ国にとりわけ焦点を絞っている。レポートではまた、トロフィーを多く 輸入しているEUの役割についても考察している。調査で明らかになったのは、1975~2003年の間に14,000を超えるヒグマの体、皮、頭とトロ フィーが世界的に取引されており(これらは総合的な年間の国内捕獲数のほんの一部)、カナダがもっとも大きな輸出国で、ロシア連邦と米国が続くと報告され ている。同時に、25のEU加盟国は米国に続く、第2のトロフィーの輸入大国であった。
いくつかの調査で、トロフィーハンティングは生息国のクマ保護のための経済的誘因を生み出している一方、1997年以来、EUでは加 盟国へのヒグマのトロフィーの輸入の持続可能性について懸念が持ち上がっている。近年EUはカナダ(ブリティッシュコロンビア州)、クロアチア、スロベニ ア、ルーマニアからのヒグマのトロフィーの輸入を一時的に停止した。ブリティッシュコロンビアからのヒグマ トロフィーの輸入はいまだ認められていない。またレポートでは、EUの輸入制限の基準について再検討し、これらの制限が生息国でのヒグマの管理やヒグマの トロフィーの取引へ与える影響について評価されている。
 皮とトロフィー、モスクワの市場にて 皮とトロフィー、モスクワの市場にて©TRAFFIC North America/Adrian Reuter |
調べられた9ヵ国のうち、ブルガリア、ロシア連邦、スロバキアを除くほかすべてがヒグマの国内管理計画を実施していた。ヒグマの個体 群サイズを推定するために用いられた方法は生息国ごとに異なり、これらは狩猟者の推定値、クマの収獲頭数の統計、専門家の意見、回帰法、マークをつけての 再捕獲や無線追跡を含んでいる。ブリティッシュコロンビア、ルーマニア、スロバキア、スロベニアの公式な個体数推定値は不正確で実際の個体数より過大推定 されているとして、国内の科学者や、または国際的な保護NGO機関によって批判されている。
「生息国ごとに管理手段やヒグマの生息状況に関する入手可能な情報量やその内容が異なるために、2つの国の状況を比べることが非常に難しくなっている」と、ナップは言う。「しかし、それぞれの国のデータの量や質が、実施されている管理の質の目安となる。」
レポートではまた、EUのヒグマのトロフィーの輸入についてthe Scientific Review Group of the EU (SRG)による決定が、程度の差はあれ、生息国のヒグマの生息状況や管理に影響を与えてきたこともわかった。時には、SRGの決定やEUによる生息国と の話し合いが前向きな結果となったこともあった。例えば、クロアチアやルーマニアでのヒグマの管理計画の発展を促してきたようだ。しかし、国によっては推 奨された管理手段の施行は遅く、適切でない。そのためSRGはブリティッシュコロンビアと、最近までのルーマニアの輸入停止の提言を維持している。SRG が特定の国からのトロフィーの輸入停止を推奨していた理由は、主に原産国で実施されている管理手段の効果について懸念を抱いていたことに関係している。こ れらは、捕獲や輸出のレベルがこの種の存続にとって有害でないことが十分保証されるために必要である。
関連ニュース
【セミナー開催報告】ペット取引される爬虫類
-上野動物園×WWF・トラフィクセミナー-
2017年09月25日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催しました。生息地の開発や、ペットにするための捕獲、密輸により、絶滅の危機に瀕しているカメやトカゲなどの爬虫類。これらの動物は、密輸される途中で保護されても、多くは生息地に帰ることができません。なぜでしょうか?こうした日本のペットショップで販売される爬虫類の取引の現状と問題について、専門家が解説。参加者の疑問に答えました。
©トラフィック
国内での象牙取引で違法事例再び
古物商ら12人が書類送検されるも不起訴に
2017年08月30日
2017年8月25日に象牙9本を違法に取引した容疑で、東京都内の古物商と従業員、その顧客ら12人が書類送検されるという事件が報道された。これは、6月20日に同じく18本の象牙を違法に取引した業者が書類送検された事件に続き、2017年で2件目の摘発となる。さらに29日には、不起訴処分となったことが明らかになった。世界では、ゾウの密猟と象牙の違法取引に歯止めをかけるため関係国が抜本的な対策に着手する中、日本国内で相次ぐ違法な象牙の取引。国内市場管理の問題点があらためて浮き彫りになっている。
©Martin Harvey / WWF
【セミナー開催のご案内】上野動物園×WWF・トラフィックセミナー
-ペット取引される爬虫類-
2017年08月23日
2017年9月9日、トラフィックは、上野動物園にて「ペット取引される爬虫類」についてのセミナーを開催します。動物園で飼育されている爬虫類の生態やペット人気の陰で絶滅の危機に瀕している種を守るための取り組みと、日本のペットショップで販売されている爬虫類の取引を巡る課題などを専門家が分かりやくお話しします。
© Michel Terrettaz / WWF
2017年08月08日
2017年8月8日、トラフィックは、日本の主要eコマースサイトでの象牙取引を調査した報告書を発表した。調査の結果、オンライン店舗のほか、ネットオークションや個人向けフリマサイトでも活発な取引が行なわれる中、現状の規制に大きな課題があることが明らかになった。今回の調査で、これまで不明瞭だった、特にインターネットを通じた象牙取引の一端が明らかになったことから、日本政府にはあらためて、違法取引を許さない包括的な規制措置を求めていく。
©Martin Harvey / WWF
関連出版物
発効:トラフィック【2017年8月】 著者:北出智美【日本語】Briefing Paper
Chi Initiative BRIEFING PAPER World Rhino Day 2017
発行:Chi Initiative【2017年9月】 著者:TRAFFIC【英語】24pp







