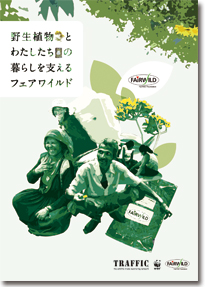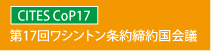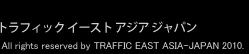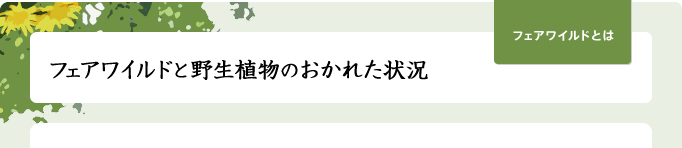
野生植物のおかれた状況
私たちが様々な形で利用している植物製品。実は野生から採集されているものも多いのです。たとえば薬用・アロマティック植物の主要な産出国である中国、インドなどで生産されているものの8割から9割は野生採集という報告があります。
一方、過剰採集や生育地の環境悪化によって、利用されている植物の3分の1の種の存続が脅かされているといわれています。
このように植物自体が危機的な状況にあることは、人々、特に自然に寄り添って生きる人々による利用も脅かすことになり、同時に、そうした植物を利用する知恵や伝統的な知識を失うことにつながりかねません。

上:©Xueyan Liu/TRAFFIC
下:©Sladjana Bundalo/TRAFFIC
日本の野生植物利用状況
日本は、世界有数の薬用・アロマティック植物の輸入国です。輸入している植物の種の内訳はわかりませんが、様々な種の植物を利用していると考えられます。
日本が多く輸入している相手国は、中国、その後インドが続きます。日本はアジアの生物多様性の恩恵を多大に受けている国なのです。
■ 薬用・アロマティック植物の輸入※(2007年)
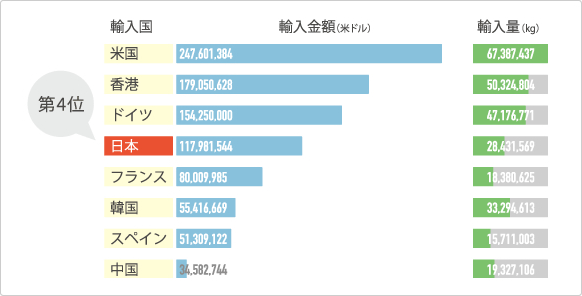
※図中の薬用・アロマティック植物は、実行関税率表中のHSコード1211<主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない)>に分類されるものとする。
日本の国際取引
薬用植物の国際取引について植物種ごとのデータが入手できるものは多くはありませんが、いくつかの種についてはその取引状況の情報を得ることができます。
たとえばワシントン条約に掲載され、香料や薬用などとして利用されている沈香Aquilaria spp.については日本への輸入が継続的に記録されています(年間数十~100件余りの輸入件数)。
また漢方薬として利用されている植物の多くは主に中国をはじめとした海外から輸入されていることが知られています。生姜、薏(よく)苡仁、唐辛子、鬱金、甘草、桂皮などとして知られる薬用植物は、そのほとんどが海外からの輸入により供給されています。
生物多様性条約と野生の薬用・アロマティック植物

©トラフィックイーストアジアジャパン
2010年に名古屋で締約国会議が開催されて以来、日本でも話題に上るようになった「生物多様性条約(CBD)」。
この条約は、野生の植物利用と深く関わっています。
2010年の会議で、生物多様性に関する「愛知目標」が合意されました。議長国の日本で採択された、日本が目標達成へのリーダーシップを担っているものです。この目標を達成する努力が様々な分野においてなされることになっているのですが、生物多様性条約の一分野である「世界植物保全戦略」がそのひとつです。
長期的に植物資源の保全と持続可能な利用を目指すこの戦略では、民間セクターの担う役割がより重要視されるようになってきました。フェアワイルドは、企業やそのほか関係者が取り扱う野生植物が持続的かつ倫理的に公正な方法で採取されたものであることを証明し、 それらの植物が使われた製品の利用を促進する、明確な原則や基準を提供しています。つまり企業がフェアワイルドを取り入れることにより、生物多様性条約が目標として掲げる野生植物の保全に、民間セクターとして貢献することができるのです。

このウェブページは経団連自然保護基金のご支援により制作されました。
薬用動植物のニュース
大手輸送関連企業の代表たちが歴史的な宣言に調印、野生生物の違法取引ルート断絶に立ち上がる
2017年05月31日
© Purple Lorikeet / Creative Commons Licence CC BY-SA 2.0
【CITES-CoP17】ワシントン条約締約国会議の附属書改正提案に対するトラフィックの見解が完成
2016年09月21日
© R.Isotti, A.Cambone / Homo Ambiens / WWF
薬用動植物に関する資料
2011年9月発行(在庫あり)
最新野生生物ニュース
2018年02月09日
香港政府が象牙取引終了を決意 実現に向けた法案が可決
2018年02月01日
象牙密輸関与の疑いで国内の販売業者が逮捕
2018年01月31日
2017年、南アフリカのサイの密猟は減少するも、1,000頭が犠牲に