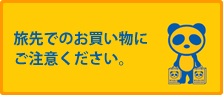2007年6月3~15日にオランダのハーグで開かれた第14回締約国会議(COP14)で採択された附属書の改正について、ワシントン条約事務局より7月26日に通達された。 詳細は、ワシントン条約事務局のウエブサイトwww.cites.orgで確認されたい。
■事務局通達No.2007/022の内容 (和訳はトラフィックイーストアジアジャパンによる)
| 1. | 条約条文第15条の規定にしたがい、2007年6月3~15日にオランダのハーグで開かれた第14回締約国会議において締約国から提案された附属書 I および II の改正について検討された。これらの改正提案は、2007年2月19日の日付で、外交経路を通じて通達によって条約加盟国に伝えられた。 |
|||
| 2. | 第 14 回締約国会議では、締約国は以下の記載について決定をおこなった。 「spp.」という略語は上位分類群のすべての種を示している。 |
|||
| a) | 次のテキストは附属書の 「解釈(Interpretation)」のセクションに含まれる。 | |||
| 「ある種が附属書のひとつに含まれている場合、その種が特定の部分や派生物だけを含むと示されていない限りは、その種のすべての部分と派生物もまた同一の附属書に含まれる。」 |
||||
| b) | 以下の分類群は条約の附属書 I から削除される。 | |||
| 植物 リュウゼツラン科 AGAVACEAE Arizona agave Agave arizonica |
||||
| c) | 以下の分類群は条約の附属書 II から削除される。 | |||
植物 |
||||
| d) | 以下の分類群は条約の附属書 I から附属書 II に移行する。 | |||
動物 |
||||
| e) | 以下の分類群は条約の附属書 II から附属書 I に移行される。 | |||
動物 |
||||
| f) | 以下の分類群は条約の附属書 I に掲載される。 | |||
動物 |
||||
| g) | 以下の分類群が附属書 II に掲載される。 | |||
動物 |
||||
| h) | 附属書Ⅱに掲載されるアフリカゾウ Loxodonta africana (哺乳綱 MAMMALIA ゾウ目(長鼻目) PROBOSCIDEA ゾウ科 Elephantidae )の個体群に関する注釈のすべては、以下の注釈に置き換えられる: |
|||
「a) |
非商業目的のハンティングトロフィーの取引 |
|||
| b) | ジンバブエ、ボツワナについて決議 11.20 に定められたものと、ナミビアと南アフリカについて生息域内(in situ )保護プログラムのための、適切で受け入れ可能な目的地に向けた、生きている動物の取引 |
|||
| c) | 皮の取引 |
|||
| d) | 毛の取引 |
|||
| e) | ボツワナ、ナミビア、南アフリカについては商業目的または非商業目的でおこなわれる、ジンバブエについては非商業目的でおこなわれる革製品の取引 |
|||
| f) | ナミビアについては装身具類に組み込まれ、ひとつずつ記号をつけ認証されたエキパという象牙加工品、ジンバブエについては非商業目的でおこなわれる象牙の彫刻の取引 |
|||
| g) | 登録された生牙の取引(ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、及びジンバブエについて、全形牙及び切断した牙)で、次の規定に従うもの: | |||
i) |
当該国で採取され、政府が在庫として所有する登録されたものに限る(押収された象牙及び原産地不明の象牙を除く)。 | |||
ii) |
事務局が、常設委員会と協議の上、輸入された象牙が再輸出されず、かつ、国内での製造及び取引に関する決議 10.10(CoP12で改正) のすべての要件に従って管理されることが確保されるような十分な国内法及び国内取引規制を有していることを認証した取引相手国に限る。 | |||
iii) |
事務局が、輸入予定国と、登録された政府所有の在庫を認証した後に限る。 | |||
| iv) | CoP12 で合意された、政府が在庫として所有する登録された象牙の条件付売買に準ずる生牙(ボツワナから 20,000kg 、ナミビアから 10,000kg 、南アフリカから 30,000kg )である。 | |||
| v) | CoP12 で合意された量に加え、ボツワナ、ナミビア、南アフリカ、ジンバブエで 2007 年 1 月 31 日までに登録され、事務局に認証された政府が所有する象牙は、上記段落 g) ⅳ)の象牙とともに、事務局の厳格な監視のもと、目的地ごとに一度の売買によって取引、発送をおこなってもよい。 | |||
| vi) | 取引による収益は、ゾウの生息域やその近隣の地域で、ゾウの保護と地域社会の保全・開発プログラムにのみ用いられる。 | |||
| vii) | 上記段落 g) ⅴ)で特定されている追加の量は、常設委員会で上記の条件を満たしたと合意された後に限り、取り引きされる。 | |||
| h) | すでに附属書Ⅱに掲載されている個体群からの象牙の取引を許可しようとする提案は、 CoP14 以降、上記段落 g) ⅰ)、 g) ⅱ)、 g) ⅲ)、 g) ⅳ)、 g) ⅴ)の規定に従って実施される一度の象牙の売買の日から 9 年間の間、締約国会議に提出してはならない。 加えて、そのようなさらなる提案は決定 14.XX と 14.XX に従って取り扱われる。 |
|||
| 事務局からの提案に基づき、常設委員会は、輸出国、輸入国による不遵守の事実や、他のゾウ個体群の取引に有害であると証明された場合、この取引の一部、あるいは全部を停止する決定をくだすことができる。 |
||||
| 他のすべての標本は、附属書Ⅰに掲げる種の標本とみなされ、その取引は、附属書Ⅰに掲げる種の標本の取引として規制される。」 |
||||
| 注:上記段落 h) の「決議 14.XX と 14.XX 」という記載は、下記の、常設委員会に向けた決議に言及しており、番号は附属書Ⅰ、Ⅱに示される。 |
||||
「常設委員会は、事務局の支持を受け、遅くとも CoP16 までに承認されるよう、締約国会議の支援のもとでおこなわれる、象牙の取引過程に関する意思決定機構を提案する。 常設委員会は、 MIKE 、 ETIS の情報に基づき、ゾウの現状、標本の取引、合法取引の影響に関する進行中の包括的な見直しの実施と、決議 14.XX で述べられた 象牙取引管理に関する行動計画と、 アフリカゾウ行動計画の施行をおこなう。」 |
||||
| i) | 附属書 II のビクーニャ Vicugna vicugna (哺乳綱 MAMMALIA, 偶蹄目 ARTIODACTYLA, ラクダ科 Camelidae )のボリビア個体群の注釈を以下の注釈に置き換える: | |||
「生きているビクーニャから刈り取られた毛の国際取引、およびこれらの毛を用いて作られた織物および製品(高級手工芸品及び編物製品を含む)の国際取引を認めることを専らの目的とする。 |
||||
| j) | 以下の分類群の注釈を、条約条文第 1 条 (b) 項 (iii) の規定に従って条約の規定が適用されるものとされる部分や派生物を特定しているそれぞれの場合に示される注釈によって置き換える。 |
|||
| - | Adonis vernalis 、 グアイアクム属全種 Guaiacum spp. 、 Nardostachys grandiflora 、 Picrorhiza kurrooa 、 ヒマラヤハッカクレン Podophyllum hexandrum 、 インドジャボク Rauvolfia serpentina 、 チュウゴクイチイ Taxus chinensis 、 T. fuana 、 イチイ T. cuspidata 、 T. sumatrana 、インドイチイ(ヒマラヤイチイ) T. wallichiana について : | |||
「次のものを除くすべての部分と派生物 : |
||||
| - | Hydrastis canadensis について : | |||
| 「地下の部分(すなわち根、地下茎):全体、部分および粉末」; |
||||
| - | チョウセンニンジン Panax ginseng and アメリカニンジン P. quinquefolius について | |||
| 「薄く切られた根および根の部分」; |
||||
| - | レッドサンダー Pterocarpus santalinus について : | |||
| 「丸太、木片、粉末、抽出物」; |
||||
| - | 附属書 II のラン科全種 Orchidaceae spp. および次の附属書 II の分類群について : 笹の雪 Agave victoriae-reginae 、アロエ属全種 Aloe spp. 、アナカンプセロス属全種 Anacampseros spp. 、アクイラリア属全種 Aquilaria spp. 、アボォニア属全種 Avonia spp. 、 Beccariophoenix madagascariensis 、ボウェニア属全種 Bowenia spp. 、コスタリカバタナットノキ Caryocar costaricense 、タカワラビ Cibotium barometz , Cistanche deserticola 、キュアテア属全種 Cyathea spp. 、ソテツ科全種 Cycadaceae spp. 、シクラメン属全種 Cyclamen spp. 、ディクソニア属全種 Dicksonia spp. 、ディディエレア科全種 Didiereaceae spp. 、ハエトリグサ Dionaea muscipula , Dioscorea deltoidea 、トウダイグサ属全種 Euphorbia spp. 、 Fouquieria columnaris 、ガランサス属全種 Galanthus spp. 、ゴニュステュルス属全種(ラミン) Gonystylus spp. 、ギリノプス属全種 Gyrinops spp. 、 Hedychium philippinense 、 Lewisia serrata 、ミエミツヤヤシ Neodypsis decaryi 、ネペンテス属全種 Nepenthes spp. 、 Oreomunnea pterocarpa 、ナンアヤマモガシ Orothamnus zeyheri 、パキポディウム属全種 Pachypodium spp. 、パナマローズウッド Platymiscium pleiostachyum 、アフリカヤマモガシ Protea odorata 、 Prunus africana 、ヘイシソウ属全種 Sarracenia spp. 、ステルンベルギア属 Sternbergia spp., メキシカンマホガニー Swietenia humilis 、 Tillandsia harrisii 、 T. kammii 、 T. kautskyi 、 T. mauryana 、 T. sprengeliana 、 T. sucrei 、 T. xerographica 、奇想天外 Welwitschia mirabilis 、フロリダソテツ科 Zamiaceae spp.: | |||
「以下を除くすべての部分や派生物 : |
||||
| k) | 附属書 II のラン科全種 Orchidaceae spp. の注釈を以下の注釈に置き換える : | |||
| 「人工的に繁殖させた次の属の交配種は、もし a) および b) で示される条件に合えば条約の規定は適用されない:シンビジウム属 Cymbidium 、 デンドロビウム属 Dendrobium 、 ファレノプシス属 Phalaenopsis およびバンダ属 Vanda : | ||||
| a) | 人工的に繁殖させた標本だと容易に認識でき、採取に起因する強い脱水や物理的な損傷、ひとつの分類群や貨物の中で不規則な成長または不規則なサイズや形、藻類や他の葉上生物 (epiphyllous organisms) の葉への付着、または昆虫または他の害虫による損傷といった、野生から採取されたことを示す徴候がない。 | |||
| b) | i) | 花が咲いていない状態で荷積みされる時、標本は 20以上の同一交配種の植物がそれぞれ入っている個別の容器(厚紙製の箱、箱、木箱または CC コンテナ( CC-containers) の個々の棚のような)で構成される貨物で取引されなければならない。;それぞれの容器の中の植物は高度の均一性と健全性を示していなければならない。;および貨物は、それぞれの交配種の数を明示する送り状のような文書が添付されていなければならない。;または | ||
| ii) | 標本ごとに少なくともひとつは完全に開花している、花が咲いている状態で荷積みされる時、 貨物ごとの最少数は必要とされないが、 標本は商業小売販売向けに、例えば交配種の名前および最終加工国を指し示す印刷ラベルの貼付または印刷包装材で梱包されているなど、専門的に加工されていなければならない。これは明らかに目に見えて、容易に検証可能であるものとする。 |
|||
| 免除に該当することが不明瞭な植物には、適切なワシントン条約の文書が添付されていなければならない。 |
||||
| l) | 附属書 II のチュウゴクイチイ Taxus chinensis 、 Taxus fuana および Taxus sumatrana の注釈を削除し、イチイ Taxus cuspidata の注釈を次の注釈に置き換える。 | |||
| 「生きた状態で鉢または小さな容器に入ったイチイ Taxus cuspidata の人工的に繁殖させた交配種および栽培品種で、送り荷ごとに分類または分類群および「人工的に繁殖させた」という文が明示された文書が添付されたものは、この条約の規定の適用を受けない。」 | ||||
| 3. | 附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲで使われる種名及び、上位の分類群は、COP14で採択された文書CoP14 Doc.8.5で言及された新しい学名命名の参考文献を反映し改正される。 |
|||
| 4. | COP14で事務局は、附属書に掲載された動物種のリストを簡素化にする必要があるという意見に応えて、アルファベット順に目、科、属を示すため、配列し直す意思を示した。この提案に対し全面的な支持があったため、附属書の改訂版ではそのようになる。 |
|||
| 5. | 条約条文第15条1 (c)項の規定に従い、COP14で採択された改正は会議後90日、すなわち2007年9月13日に発効する。同条3項に従って留保を付している締約国を除く全締約国が対象となる。 |
|||
| 6. | 条約条文第15条3項に従い、その条文の1 (c)項によって規定された90日間(2007年9月13日まで)に、どの締約国も寄託政府(スイス連邦政府)に書面の通知に従って、COP14で採択されたひとつまたはそれ以上の改正に対して留保を付すことができる。この場合、その締約国は当該種の取引に関して、条約の締約国ではない国として扱われるものとする。その他の締約国は留保を付した国とのそのような取引に対しては、条約条文第10条の規定を適用するものとする。 |
|||
| 7. | 条約第12条2 (f)項に従い、事務局は、COP14で採択された改正と、3項のもと言及されている標準準拠文献(standard references)の採択によって必要とされる変更を踏まえるために附属書 I 、II、および IIIの最新版を発行するものとする。この最新版は、2007年9月13日から有効で、この通達の後すぐに配布される。 |
|||
(最新更新日:2007年9月5日)